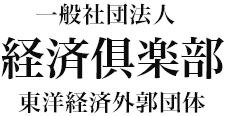倶楽部コラム
2024.07.03
経済倶楽部講演録2024年7月号 No.905
2024年7月号目次 ウクライナ戦争後のヨーロッパ 東京大学法学部教授 遠 藤 乾(5・17) 日銀は米欧の教訓を学ぶか BNPパリバ証券チーフエコノミスト 河野 龍太郎(5・24) 収束に向かうか、ウクライナ戦争 神 ...
2024.07.03
経済倶楽部講演録2024年6月号 No.904
2024年6月号目次 韓国総選挙とこれからの日韓関係 慶應義塾大学法学部教授 西 野 純 也(4・12) 中国ビジネスの新潮流 ―新消費・新ブランド・新市場を中心に 伊藤忠総研 産業調査センター主任研究員 趙 イー(王 ...
2024.05.08
経済倶楽部講演録2024年5月号 No.903
2024年5月号目次 令和6年能登半島地震の衝撃 静岡県立大学客員教授、東海大学客員教授 長 尾 年 恭(3・15) 自民党の危機と日本政治 政策研究大学院大学教授 飯 尾 潤(3・22) 「強い円」はどうして失われ ...
2024.05.08
経済倶楽部講演録2024年4月号 No.902
2024年4月号目次 「中国式外交」の影響力拡大-一帯一路とファーウェイとハマスが後押し 拓殖大学海外事情研究所教授 富 坂 聰(2・9) 今年1年の政局展望 読売新聞社政治部長 小 川 聡(2・16) ...
2024.03.04
経済倶楽部講演録2024年3月号 No.901
2024年3月号目次 『さらば、男性政治』が問いかけること 上智大学法学部教授 三 浦 ま り(1・19) より良い日本国憲法とは 東京大学社会科学研究所教授 ケネス・盛・マッケルウェイン(1・26) 2024年日本 ...
2024.03.04
経済倶楽部講演録2024年2月号 No.900
2024年2月号目次 ウクライナ戦争の三年目を見通す 東京大学先端科学技術研究センター准教授 小 泉 悠(12・8) 女子プロゴルフ改革 私の挑戦 日本女子プロゴルフ協会会長 小 林 浩 美(12・15) 戦争の時代 ...
2024.03.04
経済倶楽部講演録2024年1月号 No.899
2024年1月号目次 政治家石橋湛山の戦後史上の足跡 立正大学名誉教授、平和祈念展示資料館館長 増 田 弘(11・10) アニメは日本を救えるか 東洋経済新報社報道部記者 高 岡 健 太(11・17) 習近平は中国外 ...
2023.12.20
編集後記 2023年12月号
【編集後記】ガソリン税の二重課税問題の際、道路特定財源として徴収されている暫定税率分が一般財源として使われていることが議論になってきました。また、コロナ禍対策費も全く場違いな分野に流用されているなど、相変わらずです。とこ ...
2023.12.20
編集後記 2023年11月号
【編集後記】 コロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻で世界の関心が離れていた中東で、10月に入りパレスチナの武装組織ハマスがイスラエルに対しミサイル攻撃を行い、紛争が勃発。イスラエルの空爆でガザ地区の民間人を含めた犠牲者が ...
2023.12.20
編集後記 2023年10月号
【編集後記】 國分良成・慶應大学名誉教授のご講演では中国情報に関する興味深い指摘がありました。昨年の第20回党大会で習近平氏が出来なかったこととして、党規約の改正で「習近平思想」という表現がなかったこと、元々あった「個人 ...