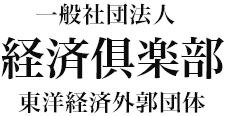編集後記
2023.12.20
編集後記 2023年12月号
【編集後記】ガソリン税の二重課税問題の際、道路特定財源として徴収されている暫定税率分が一般財源として使われていることが議論になってきました。また、コロナ禍対策費も全く場違いな分野に流用されているなど、相変わらずです。とこ ...
2023.12.20
編集後記 2023年11月号
【編集後記】 コロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻で世界の関心が離れていた中東で、10月に入りパレスチナの武装組織ハマスがイスラエルに対しミサイル攻撃を行い、紛争が勃発。イスラエルの空爆でガザ地区の民間人を含めた犠牲者が ...
2023.12.20
編集後記 2023年10月号
【編集後記】 國分良成・慶應大学名誉教授のご講演では中国情報に関する興味深い指摘がありました。昨年の第20回党大会で習近平氏が出来なかったこととして、党規約の改正で「習近平思想」という表現がなかったこと、元々あった「個人 ...
2023.08.31
編集後記 2023年9月号
【編集後記】8月には米国のキャンプデービッドに米日韓のトップが集まり、安全保障を軸に共同路線が確認されました。また、台湾を訪問した麻生太郎・自民党副総裁は講演で「戦う覚悟を持つ」と発言し、一部メディアで批判的に取り上げら ...
2023.08.02
編集後記 2023年8月号
【編集後記】ウクライナ戦争を契機としてNATOの存在感が増す中で、経済共同体から出発したEUの規範パワーの影響力がどう変化するかは注目されますが、EUでは継続的に突っ込んだ議論が積み重ねられているようです。一方、日本では ...
2023.07.03
編集後記 2023年7月号
【編集後記】とかく日本における賃上げの議論は賃上げよりも雇用が優先されるとの論調が支配的でした。しかし、コロナ禍とウクライナ戦争という戦後最大の世界的なイベントが引き金となって起こっているインフレが日本の雇用と賃金にも影 ...
2023.06.05
編集後記 2023年6月号
【編集後記】 岸田首相念願の広島サミットがおわり、いよいよ解散総選挙という運びになるのでしょうか。いつもながら解散が首相の一存でできるという憲法解釈の捻じ曲げをいつまでつづけるのかまことに嘆かわしいかぎりです。が、自民党 ...
2023.05.17
編集後記 2023年5月号
【編集後記】 ゴールデンウィーク明けの5月8日から新型コロナウィルス感染症の法的な位置づけが第2類から第5類に変更されます。それ自体は当然のこととして歓迎すべきことですが、どうしても釈然としないのは、第5類相当の感染症で ...
2023.04.05
編集後記 2023年4月号
【編集後記】 今年は4年ぶりに<RUBY CHAR="茣","ご"><RUBY CHAR="蓙","ざ">(ブルーシート?)を敷いたお花見が解禁になるようです。ただ、温暖化の影響で東京の桜は3月下 ...
2023.04.05
編集後記 2023年3月号
【編集後記】 国会で審議中の新年度予算は史上最大の水膨れ予算ですが与野党ともに身の丈に合わない赤字予算を批判する声はほとんどなく、ひたすらバラマキを求める声であふれています。赤字国債だのみの状況はつづきますが、野放図な予 ...