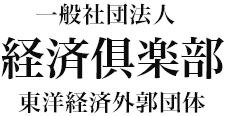講演会
2025.06.27
9月12日 演題未定
第4549回 板橋 拓己氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 講師紹介 1978年生まれ。2001年北海道大学法学部卒業。08年同大学院法学研究科博士課程修了。13年成蹊大学法学部准教授、16年同教 ...
2025.06.27
9月5日 演題未定
第4548回 塩田 潮氏(ノンフィクション作家 評論家) 講師紹介 1946年高知県生まれ。慶応義塾大学法学部政治学科卒業。「文藝春秋」編集記者を経て独立。主な近著に『安全保障の戦後政治史』(東洋経済新 ...
2025.06.13
7月11日 日本政治の課題と展望~参院選の行方、その後?~
第4547回 佐藤 千矢子氏(毎日新聞社論説室専門編集委員) 講師紹介 1965年愛知県生まれ。1987年毎日新聞社に入社し、長野支局、政治部、大阪社会部、外信部を経て、2001~05年にワシントン特派員を務 ...
2025.06.06
7月4日 ウクライナ戦争 萎む停戦の機運と今後の見通し
第4546回 小泉 悠氏(東京大学先端科学技術研究センター准教授) 講師紹介 1982年生まれ。松戸国際高校を経て2005年早稲田大学社会科学部卒。07年同大学大学院政治学研究科修了(政治学修士)。09年外務省国 ...
2025.05.30
6月27日 トランプが変える世界秩序と日本の戦略
第4545回 渡部 恒雄氏(笹川平和財団上席フェロー) 講師紹介 1963年生まれ。88年東北大学歯学部卒業。歯科医師となるが、社会科学を学ぶため、米国に留学。戦略国際問題研究所(CSIS)に入所し、以後、客 ...
2025.05.23
6月20日 半導体異変~AIバブル修正にトランプ関税が立ちはだかる
第4544回 石阪 友貴氏(東洋経済新報社編集局報道部記者) 講師紹介 1994年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒。2017年に東洋経済新報社入社。食品・飲料業界を担当しジャパニーズウイスキー、加熱式たば ...
2025.05.22
6月13日 アルツハイマー病 四半世紀におよぶ創薬の物語
第4543回 下山 進氏(ノンフィクション作家) 講師紹介 1962年生まれ。ノンフィクション作家。ネイチャーなどの科学論文に目を通したうえで、科学を人間のドラマとしてつむぎだすその手法には定評がある。科学関 ...
2025.05.09
6月6日 「トランプリスク」に揺さぶられる経済・金融市場の行方
第4542回 上野 泰也氏(みずほ証券 金融市場調査部チーフマーケットエコノミスト) 講師紹介 1963年生まれ。85年上智大学文学部卒業、法学部入学。同年国家公務員1種試験・行政職合格。86年会計検査院入庁 ...
2025.04.28
5月30日 ここからの日本の針路
第4541回 寺島 実郎氏((一財)日本総合研究所会長) 講師紹介 1947年北海道生まれ。73年早稲田大学大学院修了後、三井物産入社。83~84年Brookings研究所出向。87年米国三井物産、91~97 ...
2025.04.18
5月23日 日本経済の故障箇所
第4540回 脇田 成氏(東京都立大学経済経営学部教授) 講師紹介 1961年生まれ。東京大学経済学部卒業。同大学大学院経済学研究科修了。東京大学社会科学研究所助手、東京都立大学助教授を経て現職。主な著書に『日 ...